| 1月25日、愛媛県八幡浜市松柏中学校2年の女生徒がいじめを苦に自殺したという事例でも、教師たちは最善を尽くしていたと思う。しかし、最後は生徒の判断である。だから、普段が大事である。生きていくことのすばらしさ、かけがえのない命の大切さなど、道徳、学活の時間はもちろんのこと、あらゆる場面で、生存権を感じさせられるような指導を心がけたい。 ・困難を乗り越えていくことが成長なんだ。 |
|
| いじめの発見は難しいが、あらゆる努力は必要である。 ・「どうして親や教師に話さないんだ」という前に、自分は話せる相手か。 ・よく観察しているか(待ちの姿勢では) (給食や清掃、放課後などにいじめは現れやすい、そして情報交換を) ・普段からコミュニケーションはとれているか ・信頼されているか(よけいに悪くなる)ラポール ・相談できる環境は整っているか ・「いじめはない」と言って生徒を圧迫していないか ・生徒の声:「先生に言うと自分も悪いと言われそうで何だか怖い。 そう言われると話が続かなくなってしまう。先生は常に正しい方へ進んでいく。 それが正しいことだと自分でもわかっているけど、完全に味方になってくれるかどうか不安だ」 ・いじめの程度にもよると思うが、まずは、『全面的な受け入れ』が大事。 (スクールカウンセラーは叱ったり、説教したり、決めつけたりしない) ・生徒は「恥ずかしいこと」と思っている。 ・集団生活では、個人の価値観や考え方が違う以上、対立することは当たり前のことである。 決して恥ずかしいことではない。 ・いじめは必ず起こり得ることであり、誰にでも起こることである。 (いじめと犯罪は無くならないという意見もあるぐらい) ・教師や親はどうだろう。(いじめはしないか) |
|
| 学校と家庭、小・中の連携を強化する。(関係諸機関なども) ・卒業式まで、親は知らなかったなど。 ・一人でしょい込んでしまわない。 ・生徒たちはさまざまな個性を持っている。指導する側もさまざまで良い。 (話し合い、より良い指導、チームワークの重要性) ・共通した認識が必要。(他のクラスに入っていくのは怖い) (具体的に取り組むのは担任だが、共通理解が必要である) |
|
| 相談できる人間関係が大事である。 ・友だちの存在が大きい。(理由はどうあれ、完全に見方になってくれる) ・親子のコミュニケーション。 (何も言わなかったから知らなかったでなく、気がついて聞いてもいいのである) |
|
| 教育的配慮が必要である。 ・担任の先生が毎年変わる。 ・仲の良かった友だちと、クラス替えで別々になる。 ・事後指導を気長に、そして最後まで責任を持って。(「その後どうだ..」) (処理後から指導が始まるというぐらいのつもりで取り組む) |
|
| 最後に締めくくりとして |
|
| 原点(基本)は何だろう。 ・難しいことは何もない。 「死のうかと思ったこともあるけど、お母さんの泣き顔を思い浮かべると、とてもそんなことはできないと思った」 (人間愛、生徒愛、家族愛、これがすべてである) |
|
|
今後の課題として、他のクラスにもどのように広めていけばいいだろう。(下地づくり) |
過去の研究会での発表
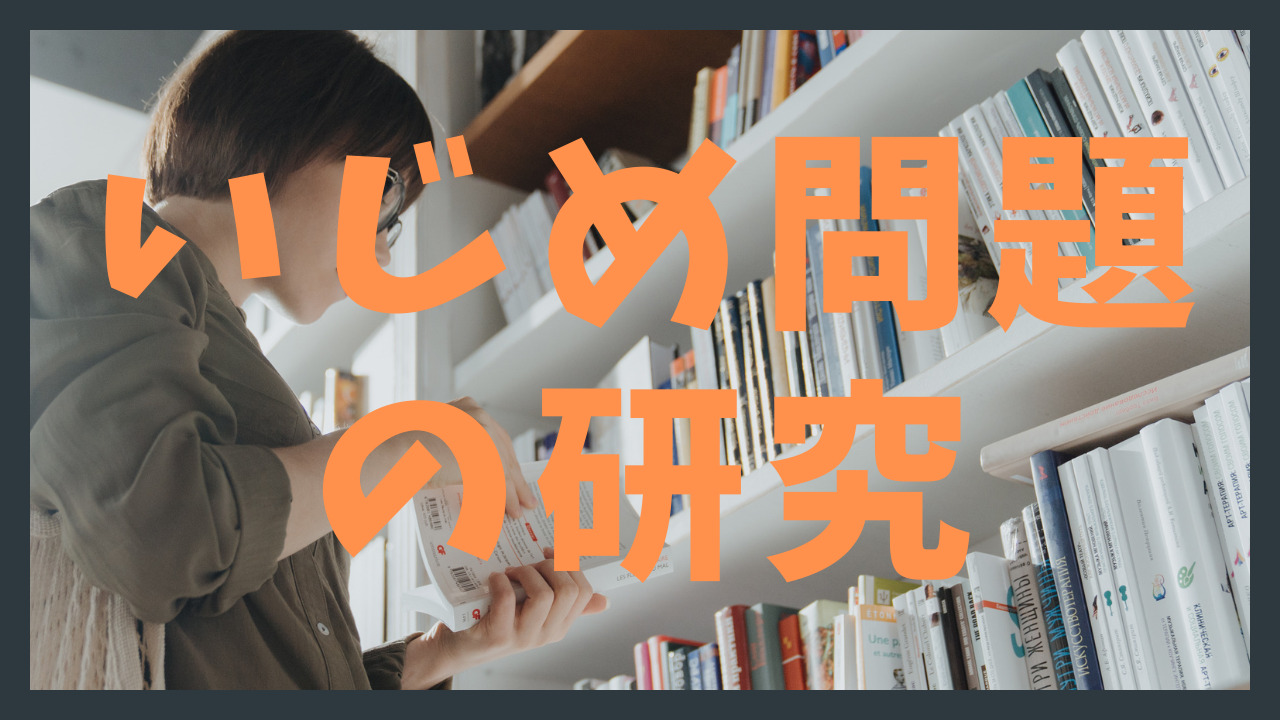 いじめ
いじめ
コメント